・開発 SCEジャパンスタジオ
・ジャンル オープンワールド+重力アクション+アドベンチャー
https://youtu.be/AG-yi24ROXE
・CMから受けた印象
重力を任意の方向に決めて飛んでいけるゲームなのだろうといった印象
ティギーウィリアムスを起用していて、428 ~封鎖された渋谷で~をプレイしたユーザーを意識して作られたのであろうか、と思った。
・どういったゲームか
わかりやすいコンセプト、重力を操る ということをうまく作りこんでいて、それを楽しめる内容
分かりやすく言えばドラえもんの重力ペンキ
フレンチコミック感のあるアドベンチャーパートが良い雰囲気
・良かった点
重力を駆使した移動、攻撃、ギミック
→移動に関しては重力を駆使して一気に移動する気持ちよさを感じられるように、高低差が非常に激しいステージになっている。
→攻撃に関して、敵がいる方向を下にすることで敵に向かって落ちていく重力キックは目標までの距離が大きいほど威力が上がる。
→ギミックは、プレイヤーが重力を操作すると周りの物や人にもその効果が及んで一緒に移動することができる
移動がメインのレースのミッション、攻撃をメインにしたバトルミッション、ギミックをメインにしたお使いミッションが用意されている
オープンワールドには必須にと思うが、マップにマーカーを付けることができるのは良い
ステージの中を移動するということがとにかく楽しい。それゆえ収集アイテムの存在が全く苦にならない。むしろ収集するという理由があるために移動を楽しむ理由が一つ増えているとさえ感じた。
・つまらなかった点
キャラクターをジャンプさせることもできるが、性能は低く、ちょっとした段差も重力操作が必要になる。
→重力操作はRボタンを押して方向を決めてもう一度Rボタンを押さねばならず、さらに小回りも聞かないのでちょっとした段差を飛びたいと思うたびに面倒を感じることになる。
それは空中での方向転換も同じで、快適に飛んでいる途中で一度止まって、方向を変えて飛んでいくという原付自動車の二段階右折のような仕様は爽快感を非常に欠く仕様になっているように思う。
エピソード5までの感想であるが、ステージに意匠的なデザインは感じても、機能的なデザインをあまり感じなかった。
極端に言えば重力がなくても、ポンプを背負ったマリオでクリアできそうだと思った。
小さい敵に重力キックが当たらない。
逆に大きい敵には重力キック連打で何とかなってしまう。
重力キックは当たったとしても演出に派手さがないため手ごたえがない。ホーミング性能も弱いように思う。
ボタンの数ゆえの仕様だと思うのだが回避行動が画面のフリックで行わなければならないのは慣れが必要。特にこのゲームは基本的にボタン操作だけですべて済ませられる仕様になっているので、回避行動のみフリックということは分かっていてもとっさに出すことは難しい。
ガンダムシリーズのようなロックオンがあってもよいと思う。
→カメラ操作が非常に難しく、重力による素早い移動で敵を見失い被弾することが多いため。
・自分ならばどう直すか
ジャンプの性能をもう少し向上させる
→ジャンプでは届かない越えられない距離や壁=重力操作を行うべき箇所をきちんと用意したうえで、ジャンプで越えてよい段差はジャンプで越えられるようにする。
攻撃をする楽しみをもっと持てるようにホーミング性能を向上させ、ロックオンの機能を実装する。
重力の中心にしたい場所はタッチで決められるようにすると良いと思う。
→落ちていきたい場所を右スティックで細かに決めることが難しいため。
→それによって回避がRボタンでできるようになるし、そうしなかったとしても画面を指で触るという操作方法自体に慣れることができる。
飛んでいる最中の方向転換をもっと楽に。
→飛んでいる最中にカメラを向けた方向に1ボタン、もしくはタッチで方向転換できるようにするのはどうだろうか。
そういった仕様になっていないのは、そうしたことで飛んでいく先を見ていなかったがゆえに起こる事故(ミスや死亡)を考えてのことであると思うが。自動車のわき見運転の事故のような。
ブログ一覧
【感想】御城プロジェクトRE~CASTLE DEFENSE~
御城プロジェクトRE~CASTLE DEFENSE~
・プレイしたきっかけ
艦隊これくしょんにハマっていた友人から勧められたことがきっかけ。
お互い城に興味があったことがあって話のネタになるかと思って始めた。
実際、城娘と実際の城を見比べながら数時間話し込むこともある。
・どんなゲームか
艦隊これくしょんの艦隊を城にしてゲーム性をタワーディフェンスにしたようなゲーム
タワーディフェンスだが、ステージに配置できる人数は最高で8人
その8人を巨大化させて守備範囲を広くして殿を守る
・良かった点
時間で回復する気を使ってキャラクターを巨大化させて強化していくゲーム性
→城娘を大きくすることで攻撃力、回復力、その範囲が強化される
→限られた人数で殿を守る(=人海戦術は通用しない)ので、戦略性が増している
最大まで巨大化させることで発動する特技と時間経過で使用できる計略があり、使い分けで状況をひっくり返すことができる
→特技と計略は、キャラクターの元になった城に因んでいるものがあるので、城好きにはうれしい
要するに、
城娘が強くなる、特技の発動によって巨大化する面白さがあり、
計略の存在で一定時間殿を守るということにも面白さが見いだせるようになっている。
殿以外にも守る対象である蔵が存在し、守り切れば報酬が増える
→限られた人数でどれだけの蔵が守れるかという楽しみもある
・つまらなかった点
チュートリアルがない
→キャラクター毎に平地、山、水などの属性?があるが、それがゲーム中にどう生かされているのかが分からない。
→計略の説明に1ウェーブ間効果持続、とあるがウェーブとは何かという説明がない
→チュートリアルがないために(というわけはないが)初期の相棒になるキャラクター(ポケモンで言うフシギダネ)が存在しない
→どんな敵がいてそれに対してどのような攻撃が有効なのかが全く分からない
出撃に必要なスタミナの消費が激しく、回復が非常に遅い
1度出撃するのにスタミナ50を消費なんてことがざらで、それを回復するのに50×5分で4時間以上かかる
→スタミナの最大値は150程度なので3度出撃すると半日プレイできなくなる
レア度の低いキャラクターを活躍させることができない
→性能が低く、進化や改造もできないためレア度3以下のキャラクターを使用する場合には高難易度のステージはまずクリアできない
難易度が高い
→イベントは序破急離結の5段階の難易度が選べるが、レア度の高いキャラクター(レベル40/80程度)で固めたパーティで挑んで考え得る最高のプレイをしたとしても急あたりまでしかクリアできない
→コンティニューは不可である
10連ガチャのうまみがない
→得点がキャラクターのレベルアップに使用できるアイテム(高難度のステージ10回分程度に相当)がひとつ貰えるだけで、レア度の高いキャラクターを引くことができるわけではない
キャラクターのレア度に統一性がない
→国宝の松本城がレア度5で、町中にちょこんと立っている神社程度の規模である広島城がレア度6など
挙動が非常に重たい
→アップデートの度に容量が軽くなっていくので改善はされているようだが、それで
フリーズが多発する
武器強化にはもとになる武器と同じレア度の武器が必要
→レア度3の武器を強化するにはレア度3の武器が必要で、レア度が低くても高くても強化に使用できない
武器の入手方法がない
→ガチャもなく、曜日クエストでの入手が可能だがどのような確率でなにが入手できるのかも明確化されておらず、白猫プロジェクトのように施設で作ることもできない
→確率で強化の成功失敗が決定するので、運が悪いとすべての武器を無駄に廃棄したという結果になりかねない
→さらに言えば、武器の強化の成功確率を上げるためには施設の強化が必要だが、その施設の強化に城娘なら34人、強化専用のキャラクターでも20人必要になる
無課金でアイテムを使用して引くことができるガチャの性能が非常に悪い
→統計ではレア度4(パーティに3人以上入れるのは辛い性能)が引ける確率すら1パーセント程度
HPが0になってしまったキャラクターは経験値が半分になる仕様
→それゆえ難しいステージに挑むほどキャラクターが育たない
・自分ならばどう直すか
ゲームの面白さ以前に、ソシャゲが流行る以前の実験的なゲームなのかと錯覚するような、ユーザーに対する配慮のなさが目立つ
タワーディフェンスとしては面白いと思うが、運営がその良さを殺してしまっている
タワーディフェンス部分をどう直すかだが、
まず初見殺しが多すぎるのをなんとかすべきだと思う。敵がどこから来るのかが全く分からない仕様を見直すべき。
例えば、
現状このようなステージだが、どこから敵が来るのかを知らないがために致命傷を負うことが多々ある。

そこで、微妙な違いだがレースゲームの障害物の告知のようにアイコンが表示されるだけでも違うと思う。

【感想】Grand Theft Auto V
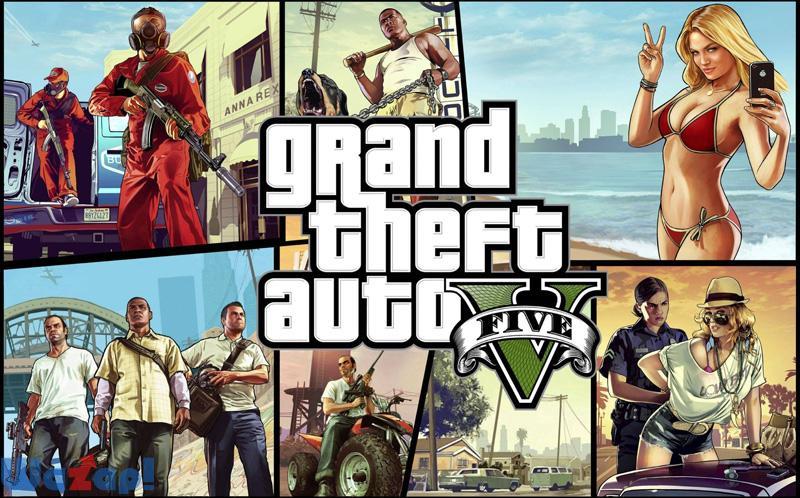
・開発 Rockstar North
・ジャンル アクションアドベンチャー+オープンワールド
・CMから受けた印象とプレイ前のイメージ
CMを見て思ったことは、想像していたよりもストーリーを押すゲームなのだろうか。ということ。
イメージは龍が如くをアメリカでやる。そんな感じに考えていた。
・実際にプレイして思ったこと
車の運転をしている時間が一番長い。というのも、大都会を舞台にしたオープンワールドゆえに、車での移動が必須。マップが広大な上に三次元的に複雑であるために道を間違えてしまって運転する時間が増えていく…。
ストーリーはあるが、車の運転のおまけといった印象。
ストーリー、ゲーム性ともに強盗することをひとつのテーマに作られているように感じた。
実際に強盗ができる店は多くない。といよりもマップが広く見つけづらい印象。
自由度が非常に高く、太閤立志伝をアクションゲームにしたように感じた。
・良かった点
自由の国アメリカでの生活を堪能できる作りこまれたゲーム性
→ストーリーを追うことでギャングとして生きることもできるし、道を外れてタクシーの運転手として生きることもできるし、株のトレーダーとしていきることもできる
性格、生い立ちの違う3人のキャラクターを切り替えて進めていく。それぞれミッションの性質が違うので、一人の主人公に飽きて来たらほかの二人にチェンジということが出来。そのうえ生き方の違う3人を操作することで自由の国アメリカを体感できる。
さらに言えば、3人のキャラクターの設定が良く練られていて、ストーリーミッションを進める度にキャラクターのことを知ることができる。
車を運転する時間が長いが、多彩な会話でその間をつないでいる。ここでもキャラクターについて知ることができる。しかし個人的には問題点でもある。後述。
戦闘中にでも装備を選んでいる間は時間がゆっくり流れる、メタルギアのオプスのような親切な仕様
ある程度の自動照準
・つまらなかった点
洋ゲーをプレイしたことがそう多くないことと、英語に明るくないせいかもしれないが英語でしゃべっているキャラクター同士の会話は字幕を見ないと理解できないが、字幕を見ている余裕が全くない。
→車の運転中に画面下に文字が出ても見ることができない。注目して見ているとキャラクター設定や重要なセリフもある。本来なら長くなる移動時間を退屈なものにしない仕様なのだろうが、キャラクターの設定などを知っておきたい自分にとっては有り難くない仕様であった。
→ついでに言うと日本語訳があまり美しくないように感じた。
ダメージを負ったときに無敵時間がなくノックバックの時間はあるため、蜂の巣にされて死亡することが多い
ミッションが終了したときにロードを挟み、ミッションのデータが消されてしまう仕様になっている
→何が言いたいかというと、所持していないものはすべて消えてしまう。それゆえにミッション中に車を自分のものにしたとしても乗った状態でクリアしない限りミッション終了時に無かったことになってしまう。
→車に乗った状態でクリアできないミッションは、ミッションの最中に自宅のガレージに気に入った車を納める必要がある。
→そのような仕様であるのに特定のミッションで登場する特定のキャラクターしか持っていない車が存在する。
×ボタンにダッシュと車のブレーキ、キャンセルが割り振られていて、ダッシュしている最中にミッション開始の電話がかかってくると意図せずに着信拒否してしまうことがある。
アメリカでギャングとして生きることのリアリティを追及したゲームだが、警察の挙動に違和を覚える。
というのも、警察は基本的に射殺することしか考えていない
→NPCの犯罪行為を見つけて通報することができるのだが、パトカーは毎回一台しか来ず警官が降りてきたと思ったら犯人に向かって容赦なく発砲する。これはプレイヤーが手配された時も同じで、近づいてきた警官に逮捕されることを警戒するのではなく、手配された瞬間にどこから飛んでくるかわからない銃弾に気を揉むことになる。
→また、正当防衛という概念が存在しないためチンピラ風の若者たちに襲われたとき反撃するとプレイヤーが手配され、駆けつけた警官にプレイヤーが射殺される。
→警官の前で犬と遊んだだけで射殺された。
また、警官の目から一定時間逃れることが手配度を下げる方法であるのだが、どこにいても嗅ぎ付けて追いついてくる。
→メタルギアでいう段ボールやロッカーのような隠れるためのアイテムや場所は存在しない
→ヘリコプターが出動してきた場合、本格的に逃げる場所がない
カメラ操作が難しい。
→キャラクターが向いている方向にカメラを向けるコマンドがなくクイックターンもないため、後ろを向くためには数歩歩きながらカメラも動かさなければいけない
マップに無駄が多い
→行く必要がない土地が多い。
・自分であったらどう直すか
広大な土地があるのだから、アイテムが入手できたり地中の埋蔵金や温泉や石油を掘り当てたり、家を自由に建てることができたりといった仕様があってもよかったと思う。
せっかくの自由度なので、何をどのくらい達成したのかを振り返ることのできるライブラリ機能のようなものがあってもよいと思う。
→一応存在するのだが何人を殺害したといった項目は人間+動物の数で表示されている
→自分であったら、破壊した車種、殺害した人間の種類や男女比、動物の種類、収支の記録などを細かに確認できるようにしたい
【感想】レッドファクション:ゲリラ
・ジャンル アクションゲーム オープンワールド TPS
・開発 ボリション
・ローカライズ スパイク
・CMを見て思ったこと
破壊をコンセプトにしたゲームのよう
ただただ派手に、見えているものをすべて壊していくのだろうと思った
・実際にプレイして思ったこと
マインクラフトの穴を掘って進む感覚に近い
壁に囲まれていて進めないとき、よくあるゲームでは壁の切れ目を探すところだがこのゲームではその必要がなくハンマーなどで影を破壊して進むことができる。そういった破壊を至る所で楽しめるゲームである。
派手さとは裏腹に無駄がなく綺麗に纏まったゲームだと思った。
・良かった点
破壊という引きのあるコンセプトを存分に生かすゲーム性
道を作る、ゲリラ活動で敵拠点の破壊、鉱石の採取など
なんでも破壊するたびにサルベージ可能な鉄くずのようなものが出現し、それがこのゲームでは通貨になるので破壊に対するモチベーションになる
道を作ることに関しては前述のように、道が閉ざされているように見えてもハンマーや爆弾で道を作ることができる
というのも、見えている建築物や車やアイテム見方も敵もすべてに攻撃、破壊ができるためである。これがこのゲームの肝である。
ゲリラ活動に関しては、随所にある敵の拠点を破壊して少しずつ敵を無力化していくことができる。逆にそれによって味方の士気が上がり、補給や援軍などが優秀になりミッションを有利に進めていけるようになる。
GTA5の後にプレイしたからかもしれないが、オープンワールドのゲームだが広すぎない。
→アジトから車で向かえばどこであっても1分ほどでたどり着けるし、ダッシュもなかなかのスピードなので車を使わずとも出かけることが苦でない。また、ステージのところどころに車が停められて、その位置取りも絶妙。
ミッションの現場へ向かうためにマップを開きマーカーをセットしマップを閉じるという作業が不要で、メインミッションの現場のみだが→ボタンを押すことで現場までの道筋がステージ、マップの両方に表示される。
・つまらなかった点
ハンマー、爆弾の万能さが悪い意味で目立つ。どちらも厚い壁、太い柱、敵をすべて一撃で破壊、殺害することができてしまう。
→また、ハンマーで殴る、爆弾で吹き飛ばすアクションにはエイムがほとんど必要ないのに対して、銃器で敵を撃つ際にはかなりシビアなエイムが要求され、ロックオンの機能もない。
破壊によって得られる通貨が少ない。
→買い物で必要な通貨を貯めるためには、気長にミッションを続けていくかミッションに関係ない破壊を相当量しなくてはいけない。
敵か味方か、グラフィックでは判断しづらい
→出てくるキャラクターの多くが砂漠のような色の装備をしていて近づいても敵か味方か判断しづらく、攻撃して倒してから味方だとわかることがある。
→味方を倒してしまうとペナルティもあるので辛い仕様である
敵に自分が見つかっているのかが分からない。
→ついでに援軍を呼ばれたのかどうかもわからない。
→援軍が来ないこともあるが、それは援軍を呼ぶ通信兵的な敵を倒したからなのか、ゲリラ活動が実を結んだ結果なのかが分からない。そのためゲリラ活動に達成感がまるでない。
メタルギアソリッド3のVERY EASYをオープンワールドにしたような印象
→メタルギアのVERY EASYはマップを移動するとアラートが解除されるがそれに似ている
→そう思ったのは、敵に見つかった状態である程度見つかった場所を離れると急に追ってこなくなるから
・自分であったらどう直すか
建物にウィークポイントを設けるのも1つの手ではないだろうか。
→現状、建物を全壊させるためには構造力学的に加重に対して役割を担っていないような壁や柱などY軸方向に立っているすべてのオブジェクトを破壊しなければならない。
→そのためにはハンマーで少しずつ破壊するか一度に設置できる数に限りがある爆弾でこれまた少しずつ破壊していくしかない。
→しかしその過程で敵に存在がばれてしまい建物を壊すどころではなくなる。
→そこで、建物の大黒柱(これを倒せば建物が全壊するというような柱)を作って、それに爆弾を仕掛けて外から起爆、建物が壊れていく様を眺めることができる仕様にする。
【感想】ZombiU
・ジャンル サバイバルホラーアクション
・開発 ユービーアイソフト
アサシンクリードの会社
・CMを見て思ったこと
WiiUのパッドを生かすために作られたゾンビゲームだろうか。
テレビ画面とパッドの両方を見ながらのプレイが必要になるのだろうと思った。
それは、テレビ画面には主人公視点の映像のみが表示され、UIは全てパッドに表示されていたため。
・実際にプレイして思ったこと
CMを見て思った通りのゲームであった。
ゾンビによって終わってしまった町からの脱出をリアルに演出している。
他のゲームと比べゾンビも主人公もすぐに死んでしまう。
・良かった点
WiiUのパッドを最大限生かそうというゲーム性が良い
主人公が持っているプレッパーパッドというアイテムがパッドとリンクしている。
→パッドに表示されているUIは洗練されていて、感覚的に使うことができる
→このゲームは主人公に与えられる情報が少ない。分かりやすいUIを手探りで理解していくことがプレイヤーと主人公をリンクさせている。
SEにかなりの拘りを感じる。聞いていて気持ちが良い。
悪い部分にもつながるのだが、2つの画面が離れているためパッドでアイテムを整理している間はテレビ画面(主人公の見ているもの)が把握しにくい。
→それが良い意味で焦りや緊張感を生む。主人公がアイテムを整理している姿がプレイヤーとリンクする
これも悪い部分につながるが、生体に反応するセンサーが万能ではないことが緊張感を生む。
→生体を感知するとパッドから音が出る。しかしそれはネズミのような小動物にも反応するし、逆にゾンビに対しても高低差があったりすると反応しないこともある。
難易度の高さをゲーム性でカバーしている
→難易度が高く主人公はすぐに死んでしまう。(例えばゾンビに噛みつかれた場合は即死したり、ゾンビに囲まれる状況がすぐに出来上がるなど) そして死亡した主人公は二度と生き返らず、ストーリーの進行状況を引きついだ別の人間が主人公になる。
→死亡した場合はその主人公はゾンビになり、プレイヤーは次の主人公を操作していき前の主人公のゾンビを倒すことでその前の主人公が持っていたアイテムを回収できる。
ゾンビも簡単に死ぬ
→ヘッドショットが容易な仕様なこともあって、簡単に倒すことができる
→しかし銃弾の数に限りがあり入手もしづらいので使いすぎてはいけない。近接に攻撃に関してはバッドのみで非常に性能が悪く発生も遅く威力も高くない。それゆえ囲まれたり多数を相手にしなくてはいけない状況で銃を使い、1対1の時には近接攻撃をすることが好ましい。近接攻撃は慣れても簡単ではないので緊張が絶えない。油断すると死んでしまう、そこが良い。
→ついでに言うと、武器や回復アイテムを買うことはできない。
スコープがある銃はゲームパッドを見ながら撃つ
→景色が見える中で見たいものをスコープで見る。そして銃を撃つ ということを表現している。
マップは広大だが、至る所がマンホールでつながっていて、一度発見したマンホールへはスプラトゥーンのイカジャンプのような感覚で移動できる。
状況によって主人公の攻撃モーションや喋り方が変わる。
→例えば、普段はバッドを振り下ろし「えい!」と言っているキャラクターが、ゾンビに囲まれた際には「うわあああああ!!!」と叫びながらバッドを振り回す といったような。
・つまらなかった点
DSの2画面と違って2つの画面が離れているので集中力が続かない
難易度の調整方法のひとつに、画面を必要以上に暗くして懐中電灯を使用することを強いている。
→緊張感を生む演出ととることも出来るが、あまりにも画面が暗く段差が見えず転落したり目の前に壁があるのに気が付かず前進し続けたりということが起こる。
→メタルギアソリッド3のオセロット戦とザ・ペイン戦の間の洞窟や、バイオハザード6の開幕に近い。特にバイオハザード6.
→難易度と不自由さをはき違えてはいけないと思う。
落ちているアイテムの性能は使ってみないとわからない
→特に2番目に入手できる銃は初期装備よりも性能が低く全く使い物にならない。
→罠を仕掛けることは良いがその武器の確認に貴重な銃弾を使わせるのはどうなのか。
→もう一つ言えばこの銃が入手できるエリアにはそれまでと違ったタイプのゾンビが出現し、この銃を使っていてはまず主人公は死亡する。
無線の指示が適当で、その通りに行動すると死亡してしまうことが多々ある
→「立ち止まるな、逃げろ」といった指示があったときにはその場に留まった方が良いなど。
無意味なアイテムが多い
→このゲームはアイテムの所持数にも制限があり上手くやりくりすることが必要になるが、このアイテムを捨てたらこういう場面を乗り切ることができない… といった葛藤は少なく、アイテムを入手してすぐに、あぁ、拾ってしまった捨てなくては…と思うことが多い。
→この辺りを上手く作ったのが風来のシレンシリーズだと思う。
バッドでの攻撃はゾンビのどこを殴ってもヘッドショットになる。
→足を殴っても頭が吹き飛ぶ。
・自分であったらどう直すか
難易度の高さを不自由さ理不尽さではなくゾンビの頭の良さや、硬い、素早い、遠距離攻撃をしてくるなどといった特徴、使用すべきアイテムなどに絡めて行きたい。
→例えば、所持できるアイテムが8つ 攻略に必須、またはあると便利なアイテムがゲームを進める毎に増えていき、回復アイテムや予備の弾を持っていくかどうかを悩ませるような。
【感想】初音ミク -Project DIVA- F 2nd
・ジャンル 音楽ゲーム
・CMを見て思ったこと
CMは見つからず。
ゲームセンターなどで他人がプレイしている姿を見ていて思っていたことは、このゲーム性で初音ミクというキャラクターを楽しむ余裕があるのかということ。
ノーツがどこから来るのか分からないので難易度が高いように思えた。
二次創作的な作品のよう。
・開発 ディンゴ
フォトカノ ポケパークWiiなどを作った会社
・実際にプレイして思ったこと
思っていた通り、背景の初音ミクを見ている余裕がない。
ポップンミュージックのように上からノーツが落ちてくるのであれば間接的視野の中にいる初音ミクを見ている余裕もあるかもしれないが、
ノーツがどこから来るのかわからないため常にゲーム画面の至る所を見ていなければならない。
難易度も悪い意味で高い。
・良かった点
初音ミクをはじめとするボーカロイドたちを全面に押し出したキャラゲーとしてはよくできている。
→3Dの初音ミクが音楽に合わせて楽しそうに踊っている。というだけでもファンには嬉しいと思う。
→曲ごとにPVが用意されているが、それは全てこのゲームオリジナルのもので、もともと動画サイトに投稿されたPVの雰囲気を尊重しつつ高品質である。
服装を変えたり、部屋にいる初音ミクを延々と眺めるモード、自分でPVを作るモードなど初音ミクを楽しむためのコンテンツは充実している。
ゲーム中、タイミングによってエフェクトや音が変化する。
・つまらなかった点
音楽ゲームとしての出来はいまいちに思う。
まず難易度が高い。初音ミクが好きなユーザーはライト層だと思うので、もう少し初音ミクに気を取られていても大丈夫な難易度にしてはどうかと思う。
難易度を上げてしまっている要因は自分が思うに4つ
1つ目は先述の通りノーツが画面のどこからでも降り注いでくる仕様。
→これによって非常にタイミングがとりづらく、反射神経を試されている気分になる。
2つ目はリンクというシステム
→1つのノーツに対して複数回タイミングよくボタンを押さなければならないのだが、このリンクの速度はBPMに依存しないためスローテンポな曲であっても急にノーツが速く動きだしたりその逆もある。
3つ目はボタンを押したタイミングとは違ったタイミングのSE
→ボタンを押してノーツに対して当たり判定が行われるタイミングとSEのタイミングがおそらく違う。
→これが個人的には致命的だと思う。
4つ目は、人間に可能なのだろうか?と思わせるような連打を要求される点。
ミッション的なものがあるのだが、それが現実的でない。
→3939コンボを決めろというものがあるのだが、1曲の最大コンボ数が250程度である。3939コンボを決めるためには15回連続でフルコンボをたたき出す必要がある。
・自分であったらどう直すか
保留。のちに追記します。
【感想】ピクミン(GC版)
・ジャンル AIアクション
・CMを見て思ったこと
当時小学生だったが、何をするゲームなのかはすぐにわかった。
運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。
小さな主人公と仲間のピクミンが大きな生物に立ち向かうゲームだと思った。
・開発 任天堂
・実際にプレイして思ったこと
シンプルシリーズ、THE 人海戦術 といったようなゲーム。
アクションゲーム、パズルゲームの要素を持っていて、とても面白い。
レベルデザインが秀逸。最終的な難易度は攻略本があっても楽にはクリアできないほどだが、その高難度すらとても心地よい。
CMの通り運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。そこに嘘偽りはないがCMで思ったほど平和ではなくむしろ殺伐としたゲーム。
限られた制限時間、日数でステージをどのようにクリアして行くのかをマップを隅々まで見回した上で検討し実行していくゲーム。
予定が遅れた場合はどのようにして取り戻していくかを考えていく。
・良かった点
ピクミンは頭が悪いようで頭が良い。
→少し距離が空いてしまったり段差につまづくとついてこなくなる。
→しかしCスティックを倒すだけで運ぶべきものを運び、戦うべき相手と戦い、壊すべきものを壊す。
赤は火に強い、青は水の中で行動できる。といった視覚的な特徴がシステムときっちりとつながっている。それは敵にも言えることで、生物っぽくない色をしている敵ほど強敵が多い。初見でもそういった情報が分かりやすい。
マップの作りこみが素晴らしい。
→どのマップも時間制限内ぎりぎりでクリアできるように作られている。
→マップ自体は全部で5つ(実質3つ)だがそれぞれスタート位置から離れれば離れるほど難しい。
オリマ―(プレイヤーキャラ)のみが最深部にたどり着くことは容易だが、必要な数のピクミンを連れて運びたいものを運んで無事に帰ろうとすると難易度が激増する。
運ぶ楽しさ。
→物を運び始めると敵がいたとしても最短距離で進もうとして、反撃もしない。道を作ることもこのゲームの面白さ。
→高いところにあるものを黄ピクミンを投げて取ってその後水の中を青ピクミンで運ぶ必要がある。そういった情報をオリマーだけでの探索で見て取って、水の中を歩けない黄ピクミンをどこから投げようかと検討して…といった活路を見出す面白さがとても良い。
戦うことについて。
→制限時間のことをよく考えてデザインされている。
→基本的にはボスキャラじゃない限り一瞬で終わるため制限時間には支障をきたさないし、ボスキャラは強くピクミンの数によっては制限時間にぎりぎり倒せない。
雑魚と言えども、初見だったり油断してしまったり大損害を被る。
→戦っているうちに行動パターン、弱点が分かってくるようにできている。
増えることについて。
基本的に倒した敵が大きければ大きいほどピクミンを増やすことができる。
倒すことにもモチベーションが湧く。
食べられること。
すぐに死亡して増殖するピクミンと敵。
→ピクミンはちょっとしたことで死亡する。それはプレイヤーのミスであったり敵の攻撃であったり。
→青以外のピクミンは水に入ってしまったらほぼほぼ死亡が確定するし、赤以外は火に触れてしまったら死亡が確定するし、敵に攻撃されても食べられても死亡する。それを避けつつ、時には人海戦術で戦いながら進む。
一日の最後にオリマ―の日記を見ることができるのもよい。
→その日回収したパーツの設定や、遭遇した敵の考察、タイムリミットが迫ってくると切羽詰まった内容になったりしてとても盛り上がる。最後のプレイから日が経ってしまってもそれを読むことで何をしていたのかを思い出すことも出来る。
リアルなグラフィックと、敵の捕食モーション。
→存在しない世界をとても細かに作りこんでいる。世界観や敵の生態に関しての設定を細かに作りこみ、それを忠実に再現している。
チャレンジモードの存在
→同じマップで違う敵の配置とルール。また、理論的な最高スコアがあるので目標になる。
・つまらなかった点
ピクミンがアイテムを運び、自分の色の家のようなところにそれを入れてピクミンが増える仕組みなのだが、複数の色のピクミンが運んでいる場合は何ピクミンが増えるのかが分かりにくい。
→赤ピクミン10匹、青ピクミン11匹で運んだ場合は青ピクミンが増えるのだが、小さなピクミンが何匹ずついるのかが把握しづらい。
→運んでいる最中に表示される色を変えるという手段により、2以降で解消された。
同じ平面にいる敵とは戦いやすいが、空中にいる敵には投げたピクミンを非常に当てづらく雑魚だとしても時間とピクミンを持っていかれることが多い。
黄ピクミンの個性が薄い。高く飛ばさなくてはいけない場面が少なく、爆弾岩を唯一扱うことができるも爆弾岩の数も少ない。
→電気による即死が加わったため2以降で解消された。
パーツを手に入れることで得られる恩恵がない。
→○○を手に入れたので△△ができるようになった!といったような。
→2で解消された。
・自分であったらどう直すか
敵や破壊すべき壁に対してロックオン機能があると良いのではないかと思ったが、3で実装された。
全体的にレベルが高いゲームで、直すところがあるのだろうかと感じるほど。
1で完成しているように感じたが、2では進化というよりも1とは違ったゲーム性を確立していた。
【感想】ピクミン2(Wii版)
・ジャンル AIアクション
・CMを見て思ったこと
ピクミンの数が増えたのだなあ… 約束された神ゲーが発売されるなあと思った。
ゲーム性については特に変わりないように感じた。
・開発 任天堂
・実際にプレイして思ったこと
まず思ったのが、操作方法が全く変わっていないということ。
説明書を読んだ記憶がないが、快適にプレイできるシンプルさが良い。
時間制限をなくしたことで、制限時間の中でいかに効率よくクリアするかを考えるゲームから、いかに犠牲を出さずに丁寧にプレイするかを考えるゲームになった。
1が好きか2が好きかで派閥ができそうなくらい、どちらもよくできているが別のゲーム。
・良かった点
操作性については1に同じ。
ピクミンの種類、敵の数が増え、攻略する楽しみが増えた。
孤独じゃなくなった。
→ロケット、相棒との会話が追加されたことによって生物や世界観だけでなく、キャラクターも楽しめるようになった。
BGMの完成度は相変わらずだが、さり気ない切り替えが上手い。
ピクミンがさらに頭が良くなった。
→勝手な行動を慎むようになった。
収集するものが増えたが、そのひとつひとつに対するネーミングセンスと解説が非常に面白い。
→我々の世界では乾電池であっても、それがオリマ―たちの視点ではどう見えているのか。確認するのが面白い。
ピクミンを掴んだまま、掴んでいるピクミンを変更できる。
チャレンジモードでは専用マップが用意され、これもまた上手く作られている。
→余談だが、このころから任天堂の2人以上で遊ぶゲームのクオリティが高くなったように思う。
・つまらなかった点
1で特に強かった生物たちがリストラされ、続投となった生物も大部分が行動が遅くなったり隙が大きくなったりと非常に弱くなった。
→その代わりに○○ピクミンでなければ勝つことができないといった生物が増えた。
噴火口など、ギミックの破壊が可能になった。
火と水と毒に関してはピクミンが食らっても救済することが出き、面倒なだけの存在になりいざとなればごり押しもできるようになった。
→電気に関しては即死であり、他のギミックの弱体化もあって電気を持つ敵は雑魚であっても非常に強い。
赤ピクミンが居場所をなくした。
→赤ピクミンの良いところは火に強く攻撃良くが高いところ。しかし炎の弱体化、高火力の紫ピクミン、コッパチャッピーの登場により、いなかったとても困らない存在になってしまった。
→オリマーによるパンチ攻撃が非常に強く、時間制限がないこともあって、ピクミンを連れてマップを歩くときには敵がもういないこともある。
敵を石化するゲキニガスプレー、ピクミンを覚醒させるゲキカラスプレーの存在
→あまりにも便利で、せっかくのゲームバランスを崩壊させるアイテム。
→使わなければよいだけだが、使うことが前提に作られているような敵も存在する。
運搬に紫ピクミン100匹を要するアイテムがある。また、紫ピクミンでなければ倒せない敵が非常に強い。
→紫ピクミンは入手がしづらく、100何度も同じマップに潜りノーミスでのプレイが要求される。
→紫ピクミンでしか倒せない敵はどのマップでも時間経過で現れどこまでも追ってくる。ほんの2~3秒で100匹のピクミンを殺傷する力を持っている。
・自分であったらどう直すか
難易度を下げたために、ピクミン同士でのバランスが取れていない。
即死しない、さらに救済が可能という仕様によってピクミンの個性が死んでしまっている。
即死を再度実装するか、マップのデザインを変えることで即死しないものの救済ができない構造を作るなど。
それは3で解消されたように思う。
【感想】ピクミン3
・ジャンル AIアクション
・CMを見て思ったこと
画質の向上、リアルさを視覚的にも追及してきたのだなあと思った。
・開発 任天堂
・実際にプレイして思ったこと
あまりにグラフィックがリアルで、補色を使って隠れている生物に不意を打たれることがある。
1に近いゲーム性に、2のようなキャラクターを複数人にしたことで生まれるマップ攻略への深み、食材を探し食料を自足するという時間制限の設定とゲーム性をうまく組み合わせた仕様。
ピクミン:ピクミン2 = 8:2 ほどの割合で混ぜたような作品。
今作は3人でどれだけ効率よく仕事をこなすか。これにかかっている。
・良かった点
それぞれのピクミンの特性を生かしたギミックを上手く作っていて、前作のようにいらない存在のピクミンがほぼいない。
→攻撃力の高いピクミンが今作にも存在するが、敵に張り付くことができないという短所も持っていて赤ピクミンの居場所がきちんとある。
行ったことのある場所はWIIUパッドのマップに表示され、誰々はここに迎えと指示を出すことができる。
→あいつがあそこに着くまでにこいつはここを何とかしよう。といった楽しみ方になる。
ラスボス攻略には全色のピクミンが必要になる。
→それぞれのピクミンの良さを理解していないと攻略が難しいように作られている。
ロックオン機能が実装され、やりたいことを一度に全員に行わせることができる。
・つまらなかった点
使わなければよい機能だが、やり直しができる。
→その日をやり直すことも好きな過去に戻ってその日からやり直すことも出来る。
→初心者、やりこみたい人間にはありがたい仕様だが緊張感が一気になくなる。
ピクミンの生存力が強い。
→前作だったら死んでたなあ…と思う場面がとても多い。
1人でプレイするのと、2人でプレイするのではボリュームが全く違う。
→1人プレイではクリアまでのプレイ時間は8時間程度。2人プレイのやりこみは数十時間かかる。このゲームはその場にいないと2人プレイはできないので、一人暮らしや一人っ子には辛い仕様。
生物の設定がよく練られていない。
→プレイヤーの想像と創造におまかせします。になっている。
・自分であったらどう直すか
相変わらずよくできたゲームである。
アクションの難易度は下がったものの、3人を上手く動かす、3人であるからこその攻略方法の模索が非常に面白い。
設定やキャラクターに問題があるようにも思うが、ゲームとしては完成されているように思う。
もう一度プレイしてみます。
【感想】東方文花帖 〜 Shoot the Bullet.
・ジャンル 弾幕系シューティングアクション
・開発 上海アリス幻樂団
・CMを見て思ったこと
CMなし
ただどういったゲームかという説明を見たときに、弾幕シューティングの避けるという楽しさを抽出したゲームだと思った。
・どんなゲームか
一般的な弾幕系シューティングゲームである『文花帖(ゲーム)』より前の東方Project作品とは、システムが大きく異なる。
『文花帖(ゲーム)』は、被写体と被写体が放つ弾幕を写真撮影するゲームである。各シーン(ステージ)ごとに規定の枚数ノルマが設定されており、制限時間内にそのノルマの分だけ被写体を撮影することでクリアとなる。敵は弾幕を放ってくるので、それを避けながら被写体を撮影することになる。 wikipediaより
新聞屋さんの女の子が、敵を撃つ代わりに近づいて写真を撮る。
相手の弾幕をボムの代わりに写真を撮ることで消す。
そういうゲーム。
・実際にプレイして思ったこと
作品の色は違えど、繰り返しプレイすることで活路を見出し上達したことが実感できる何殿調整はシリーズを通しても特に素晴らしい。
今作には難易度選択が無いので、根気が必要になる段階が相当早めに来る。全11何度で4ステージあたりからコンティニューしてトライ&エラーが始まる。
・良かった点
弾幕STGでは必須になりつつあるシステムであるボム。
そのボムを使って弾幕を消すことで活路を切り開くという点に特化したゲーム性が今作の面白いところ。避けて撮る。が面白い。
東方シリーズ通して言えることだが、攻略の方法をゲームオーバーを繰り返しながら探していくところが面白い。
→アクションゲームよりもクイズゲームに近い感覚があるような気がする。
→今作は従来のシリーズとは違い敵の弾幕をボム(写真を撮ること)で消すことが前提のデザインであるため、難易度はかなり高い。だが、繰り返すうちにどうすれば良いのかがきちんと見えてくるようにできている。
→10回プレイすれば活路が見いだせ、100回~500回ほどのプレイでそれを実行できる程度の難易度。
→後述するが、今作は作者が意図して作った活路を探すよりもプレイヤーが気合でなんとかするケイブ感がある。
当たり前のことのように思えるが、敵ごとに音楽、弾幕の特徴、弾幕のグラフィックが違うしどれもクオリティが非常に高い。
→また、1キャラの攻撃パターンが多く、その攻撃ひとつひとつに名前がも魅力のひとつ。
→今作はキャラクターを掘り下げた演出が特に多い。
写真を撮るという設定もゲーム性に盛り込んでいて、
一枚写真を撮るごとにフィルムを装填する必要がありその間写真を撮ることが(弾幕を消すことも)できず、低速移動よりも低速の移動をすることで自キャラのフィルム装填時間を短縮できる。
→このシステムによってリスクとリターンを楽しめる。
また、弾幕を数撃って当てるゲーム性から撃たずに避けて撮るというゲーム性にしたことで、1枚写真を撮ることに意味を感じやすい。
新規キャラクターがいないが、それを弾幕の種類の多さでカバーしきっている。
・つまらなかった点
キャラクターを愛しているだけでは足りない、難易度の高さ。
→弾幕STGが得意であっても特殊なゲーム性ゆえにクリアはとても難しい。
指定の写真が撮れていない場合に失敗を意味するSEが鳴るのだが、これは必要ないように思える。
→やったか…?だめか…。といった思考をしている暇もないため。
→プレイ中何千回と聞くことになるのだが、聞くたびに突き放されるような気持ちになる。
東方シリーズの弾幕は追従してくるタイプと、特定の座標にめがけて飛んでくるタイプが多いが、今作はランダムに飛んでくる弾幕が多い。
→レベルデザインは弾幕の量に依存しているように思う。
・自分であったらどう直すか
写真を撮る、弾幕を消すということに特化しすぎて、
弾幕を避ける、ということに対するアプローチが足りていないように思う。
何度が高くなると、フィルム装填の時間をどれだけ短縮したとしても間に合わないくらいの弾幕が降り注ぐので弾幕を消して活路を見出すにも限界が来る。
消せば避けられる。
消さなくても避ける道は見えている。
そういった弾幕を作りたいと思う。
しかしSTGは制作側が作った不可能をプレイヤーが突破していくという楽しみ方もあると思うので、なかなか難しい。
余談。
このゲームでは自キャラとボスの1対1の対面の会話以外からは、そのボスがどういう娘なのかを知る手段がない。
だが、二次創作に全く触れない自分にも好きなキャラクターはいる。
それは凝ったビジュアル、音楽にも関係があるが、このキャラクターが好きだと特に感じる瞬間は弾幕に殺される瞬間である。それも何度も何度も殺されるたびに好きになっていく。
これについて。
とある人物と話して納得がいったのだが、
そのゲームにおいて、「価値のある、もしくは価値を見出せるキャラクター」は好きになれる。ということがあるようだ。
ソシャゲでいうレア度の高いキャラクター、RPGやアクションゲームなどにおける強いキャラといった具合に。
このゲームは、先述したが不可能に思われることを可能にすることが面白い。なので、このゲームでのキャラクターの価値は、その不可能を可能にした時の気持ちよさの度合いが大きいほど高い。
それゆえ、強い相手ほど好きになりやすいように思う。
【感想】ぷよぷよ!!クエスト
ランク200までプレイしました。
画像のアップロードが上手くできませんでした。後日もう一度試みます。
・ジャンル パズルRPG
・開発 セガ、セガネットワークス
・CMを見て思ったこと
ぷよぷよのような何か。
CMからは、ぷよぷよのキャラクターが全員集合していて、シリーズファン向けのゲームのように思えた。
・どんなゲームか
レア度は1から6まで。
ぷよを5つまで選んで消す。
上からぷよが落ちてくる。
同じ色のぷよが4つ繋がれば消えて、消したぷよの色と同じ色のキャラクターは攻撃ができる。
落ちてくるぷよはランダムなので、パズルゲームというよりも運ゲー。
・実際にプレイして思ったこと
なぜ、ぷよぷよのゲーム性でこのデザインであるのか。
何が言いたいかというと、このゲームは横に長く縦に短い。
ぷよぷよは縦にぷよを積むことで連鎖を起こすことを楽しむゲームであると思うのだが。
下は実際のゲーム画面。

・良かった点
つまらなかった点にも繋がるが、メインもモブも関係なくシリーズを通したほぼ全てのキャラクターが登場する。
本家での人気キャラクターの性能が非常に高い。
UIはとても快適。自分がプレイしたどのソシャゲよりも使用しやすいと思っている。
・つまらなかった点
ガチャで手に入るキャラクターは週に6人ほど追加される。この1年見てきた感想としては、ほぼほぼぷよぷよ!!クエストオリジナルのキャラクターで、ステータス、スキルを見てもそれらに実用性は無い。
→キャラクター1人につきレア度が3~6までが実装される。そのため、1週間でガチャから出てくるキャラクターは6×4で24種類追加されることになる。1か月で96種類。1年で1000種類以上の無能なキャラクターが追加される。
→それゆえに欲しいキャラクターを引き当てることは至難。10連ガチャを回したところで無能なキャラクターのレア度6が手に入る。おかげで課金しようとは思えない。
ぷよぷよは場を作り連鎖を決めていくゲームだったのに対して、ぷよぷよ!!クエストは初期配置とランダムで落ちてくるぷよの色が全てを決める運ゲーになってしまっている。思考が入り込む余地はほぼ無い。
・なぜ続けられたか
超初期にこのゲームを始めたユーザーのみが入手できるキャラクター、カーバンクルの存在。
→カーバンクルはスキルで全ての相手の全ての行動を3ターン封じることができる。
→このキャラクターは1ユーザー1体までしか所持することができないが、超初期に始めたユーザーのみ2体所持できる。自分は2体持っていたので、実質相手の行動を6ターン封じることができるこのキャラクターのおかげでクリアできないクエストが無かったため、ぷよぷよシリーズが好きなこともあって続けられた。
初期に実装されたキャラクターは高性能なものが多くガチャを引く必要が全くない。
→自分は2014年までに実装されたキャラクターしか使用していないが2016年7月現在クリアできないクエストは1つもない。
・自分であったらどう直すか
ぷよぷよというゲームをもとに作られた別のゲームになってしまっている点をどうにかしたい。
1画面でぷよぷよ画面、味方パーティ、敵パーティを表示させているためにぷよぷよの画面が横長になってしまっている。
表示の仕方を変えることで解決できるだろうと思う。
極端に修正したので、難易度は下がってしまうだろうが連鎖が楽しいゲームを作るならこれくらいやってもいいと思う。キャンディクラッシュのような感覚でプレイすることになる。

【感想】ライトを消すだけの高時給な宿直
ネタバレ注意。
・ジャンル アドベンチャーゲーム
フリーゲームである。
・CMを見て思ったこと CMなし
フリーゲーム紹介のサイトを見ていて、
・開発 夜雨どっと
RPGツクール2000で作成された
・実際にプレイして思ったこと
一人称の視点で一本道を歩いて、電気がついている部屋を見つけたら電気を消していくゲーム。
エレベーターで1階から3階までを行き来する。
・良かった点
音響にかなり気を使っている。
→一歩進むごとに気持ちの良い足音が鳴る
→BGM、足音以外のSEも高品質。
エレベーターにある張り紙が、通常時にはセクハラ禁止だったものが緊急時に強姦禁止になっていたのは良かった。
→視覚的、聴覚的な恐ろしさを含みつつ、こういった矛盾で怖がらせる仕掛けが自分は本当に好きである。
→ひぐらしのなく頃にの綿流し編のラスト、死人が出歩いていない限り説明ができない事象が起きている。といったような。
エレベーターに乗りフロアを変えれば安心と思っていると、エレベーターが止まりノックが聞こえてきたときは震えた。
・つまらなかった点
ゲームオーバーもゲームクリアもない。
→クリアは存在するのかもしれないが、電気を消すべき部屋はなくBGMも一切再生されなくなったので気持ちが切れてしまった。
電気がついている部屋が3フロアの数ある部屋の中でひとつしかない。
BGMが盛り上がってきて、そろそろ何かが起こるのではないかと思っていても何も起こらないことが多い。
→序盤のうちは緊張感から安心する。その安心に付け込んでくるのではないかと勝手にまた緊張する。しかしやはり何も起こらず安心する。
→これを繰り返しているうちに慣れてしまう。
音響に気を使っているが、霊的存在が現れたときに聞こえてくるのは足音のみ。
・自分であったらどう直すか
緊張、安堵の気持ちの波を上手く利用したゲームを作りたい。
プレイヤーが、
来るぞ…と思ったときに怖がらせる。
来るか…? あぁ、来なかったか。と安心したときに怖がらせる。
不意打ちで怖がらせる。
緊張しているうちに連続で畳みかける。など。
一人称視点で進んでいくゲームでは、ノベルゲームと違ってプレイヤーが歩かなければ怖がらせることができないので作るのが難しいのかもしれない。
アクションの入ったホラーゲームをプレイしたことがあまりないので、勉強のためにプレイしてみようと思う。
【感想】ステージ1コンプレックス
・ジャンル アクションゲーム
・CMを見て思ったこと CMなし
・開発 IN
アクションエディター4で作られた。
https://freegame-mugen.jp/action/game_4953.html
・実際にプレイして思ったこと
非常に面白い。
プレイヤーに同じステージを繰り返しプレイさせる、ということをよく考えて作っていることがよくわかる。
難易度は非常に易しい。
残機性ではないので、ミスしてもストレスなく再チャレンジできる。
再チャレンジはスタート地点、もしくは到達したチェックポイントから。
・良かった点
前述したが、同じステージを何度も遊ぶことを考えてデザインされている。
非常によく練りこまれたマップデザイン。
→敵、足場、即死ギミックの配置が秀逸で、ぎりぎりでやりたいプレイングができるように作られている。
HP制で、4度目のミスで自キャラが死亡する。
→ステージには3か所程度、ミスしやすいゾーンが存在する。同じステージを繰り返しプレイするので、ステージに殺されることは減っていく。しかしレベルごとで変わるギミックによって初見でのノーミスは難しい。
敵もシンプルだがよくできている。
→敵は点滅してから攻撃してくる。
→色ごとに違ったアクションを起こしてくる。
・つまらなかった点
難しいステージの後に簡単なステージがあり、難易度の上昇を期待しているプレーヤーが肩透かしを食らう。
→強制スクロールで画面端に追いつかれたら死亡といったステージの次に、無敵の味方が敵、即死ギミックを全て破壊してくれるステージが始まる、といった。
マップ自体が広くない、残機は無限、更にはHPがあるために、慣れてしまうと初見でもごり押しで進めていける。
→HP残り1になるまで思考停止でチェックポイントを目指して、その後自殺、チェックポイントからHP満タンでスタートできる。
唐突に始まるボス戦。
→何をすれば勝てるのか、もっと言えばグラフィックがそれらしくないのでボスを足場なのかと勘違いした。
→ボスのHP表示もない。
・自分であったらどう直すか
よくまとまっているが、グラフィックが物足りない。
自キャラのグラフィックも立ち、走る、ジャンプの3種類。おそらく全部で5枚程度。
敵のグラフィックは1種につき1枚。
ボス戦が分かりづらかったので、ボス戦が始まるときはそれ用の演出を用意する。
【感想】鬼に好かれる
ネタバレ注意
・ジャンル アドベンチャーゲーム ヤンデレ風ゲーム風ノベル
フリーの作品
・CMを見て思ったこと
CMなし
紹介されているサイトを見たときには、
女の子との平和な日常:非日常=4:6くらいの作品かなと思った。
○○風、というジャンルのゲームの企画を考えていたこともあって興味を持った。
・開発 午後のお部屋
吉里吉里で開発されたゲーム
・実際にプレイして思ったこと
スタジオメビウスのSNOWのような始まり方。
ヤンデレ風というよりも考え方、行動が100か0しかないメンヘラ風味なヒロイン。
女の子と男の子いうよりも、オウムとナウシカのような関係を見ているような気持ちだった。
・良かった点
二重人格のヒロインとその設定。
人間の娘は優しく気が小さい、追う一つの鬼の人格は凶暴。
だと思わせて、その実は
鬼の娘は優しく面倒見もよく、人間の娘はどす黒い感情を持ち合わせて危険。
その発想はとても良い。
人格は人間と鬼だが、体は人間である。という設定を上手く利用している。
個人的にはこの設定だけでごはん3杯食べられるくらい好き。
・つまらなかった点
BGMのないシーンがとても多く気になる。また、唐突に流れ始めるBGMの音量が大きく音割れしていることが気になり文章に集中できなかった。
描きたいシーンを盛り上げるためのシーンが見られなかった。
→一人称で物語は進行していくのだが、それが主人公とヒロインの姉の視点で進んでいく。そのためにヒロインよりも、ヒロインを敵視する彼女の姉に感情移入してしまう。
→それゆえに、主人公がヒロインを屋敷の外に連れ出したというよりも、邪魔者を押し付けられて屋敷を追い出されたように感じた。
HPでは女の子の可愛さを押したような紹介のされ方であったが、グロ描写が強すぎてほかのことを覚えていない。
どんな手段を使ってでもあなたを手に入れたい。といったセリフがあるのだがその手段が主人公に不自由な二択を強いること、というところが個人的には好みではない。
→それに対する回答は筋が通っていてよかった。
登場人物は5人、しかし立ち絵は1人。
また、ヒロインは鬼の目を持っている設定だがそれらしいグラフィックは無し。
主人公は主人公で、後先考えずに不倫をしたは良いがある時に不倫相手に結婚を迫られておろおろしている男性のよう。
→ひとつの例えでしかないが、その様を描くのだとしたら不倫相手と甘くて苦い快楽に落ちていく様を描くべきだと思うのだがそれもない。
ヒロインが主人公に嫁ぐとなったシーンでのヒロインの立ち絵の表情はセリフに反して困惑している。
・自分であったらどう直すか
日常の描写があまりにも希薄で、非日常シーンの山場に来た時に思うことが少ない。キャラクターも好きになれなかった。
→設定を上手く使うための伏線を日常のシーンで印象的に敷いていき、非日常のシーンでそれらを回収していく。
→さらにそうすることでキャラクターを掘り下げることができる。
ヤンデレを気軽に堪能できるゲーム、というわけではなかった。
→ヤンデレの良さを研究する。
設定と文章だけではノベルゲームは成立しないと痛感した。
→音、絵、演出は文章を引き立てもするし良さを損なう原因にもなる。
→使い方、品質に拘る。
【感想】東京ゲームショウ2016
東京ゲームショウ2016 感想
写真はありません…。
今回初めてのゲームショウでした。
ゲームがどうとかっていうよりも、統一性なくただただ感じたことを書き連ねます。
まず会場に入って、これだけのユーザーが来場するのか…と驚きました。
どのブースにも沢山、本当に信じられないくらいたくさんの人がいて、まだまだゲームも捨てたもんじゃないなあと改めて感じました。
ここからはブースで感じたことを。
プロトタイプとインテルとソニーを主に見てきたのでそれを。
その中でも驚いたのがプロトタイプのブース。
今回扱われていた作品がKeyのAIRとRewrite、Innocent GreyのFLOWERS、FrontwingのISLANDなどで、AIRとRewriteの人気もあってか盛況だなあと感じました。
それらふたつのゲームは、ADVとしてのゲーム性やフローチャートの在り方ではなくシナリオに全力を注いでいる作品だと思います。
正直、シナリオがどんなに完成度が高くても「これはゲームである必要があるのか?」とプレイしている最中に思うことが多いので、文字を読ませるゲーム(ADVとは別)に対して勝手ですが限界を感じていました。1ユーザーとして。
なので、大勢集まったブースを見て前述したように、まだまだ捨てたもんじゃないなあ。と思いました。
まあ、AIRという作品はアニメが多くのファンを作って、今日はその中の数%が来場していただけかもしれませんがね。
しかしながら客層のマナーの悪さは目に余るものがありました。特にプロトタイプは。
周りが完全に見えてない人だらけ。列も作らないですし、企業の方の注意は無視しますし、暴言まで聞こえてきました。
僕はInnocent Greyが好きですしAIRも大好きなのですが、この人たちが同士というか、同じ作品で涙を流してきた人たちなんだなと思うととても悲しかったです。
さて、次に行きましょう。
プロトタイプの向かいにあったインテルのブース。
ブースが大きかったこともありますが、オーバーウォッチの展示やプレイの実況は盛り上がっていたなあと思いました。
オーバーウォッチについては、スプラトゥーンのような見ているだけで面白いとは思えない。と思いました。
僕は基本的なルールや画面の見方を知っていたので今のプレイがすごいだとか、そう行くのか…!とか、そういう風に思えたのですが、連れは全くオーバーウォッチに関しての知識がない状態でその実況を見ていて退屈そうでした。
「ルールも画面の見方もよくわからない。面白そうに見えない」
と言っていたのが印象的でした。
オーバーウォッチ自体はキャラゲーの要素をFPSに取り入れたことで遊びに幅を持たせた面白い作品だと思っていますが、プレイ画面からはそれが分かりづらいのかなあと思いました。
先ほども一例に出しましたが、スプラトゥーンのような初見でも1戦見ればルールを把握してそのままコントローラーを握ればすぐ遊べる。そんなゲームはやはり凄いです。
と、なんだかんだと言いましたが帰り道でオーバーウォッチ買いました。やりたいと、僕は思いました。ええ。
ソニーに関してですが、見たのは一作品です…。
NEWみんなのゴルフを見てきました。
僕は自称みんゴルガチ勢なので、とても気になっていました。
率直な感想はゴルフ部分に進化はなかった。と、相変わらずみんな向けではない高難易度ですかね。
前者はゴルフという、ボールを打ってカップに入れるという目的と手段が完成されているスポーツをテーマに作られたゲームなので、まあ仕方ないのかなあとは思いますが…。
ゴルフのような新しい遊びを作ってゲームにしてしまうとシリーズ最新作!の看板が掲げられませんしね。
とは思いつつも、ゴルフを扱ったゲームはみんなのゴルフ6で完成していたのだなあと少しやるせない気持ちになりました。
ゴルフ以外の部分は進化(迷走?)していて、オープンワールドなホールをカートで走ったり、一緒にストロークを回っているプレイヤーもアバターが画面に表示されていたり(前作は打ち出されたボールの軌跡だけだった)と、仕様は変わっていました。
リアルさと、オンラインでのロビーの快適さには前作、前々作から力を入れているのを感じていました。しかし、一打終えたらカートを運転してボールの落ちたところまで行くことって、みんゴルのプレイヤーがやりたいことなのかなあ…?と疑問に思います。
また、ストローク中に他プレイヤーのアバターが表示される仕様もプレイヤーには煩わしいなあと思います。特にパターではそれが顕著。
難易度については、初見では絶対に分からないUI、相変わらずシビアなゲージが健在です。
うーん。不安。
買いますしやりこみますけどね。
と、はい。
そんな感じのゲームショウでした。
書きたいことはたくさんありますがこのあたりにしておきます。
他にもいろいろと見て回ったので、何かこれ聞かせろみたいなことがあったら遠慮なく。
【感想】serial experiments lain
serial experiments lain
ネタバレ注意
・ジャンル アタッチメントソフトウェア
・CMを見て思ったこと
CMではなくアニメを見て購入を決意。
アニメの内容が1mmも理解できなかったので補完として。
漫画、アニメ、ゲームがそれぞれを補完しあう作品。
・開発 パイオニアLDC
・実際にプレイして思ったこと
狂気を感じる名作、ごきんじょ冒険隊を作ったパイオニアが狂気を前面に押し出した作品。
『存在する』ということの意味、記憶とはただの記録である。という2つの事柄を掘り下げていて哲学や答えのないことについて考えることが好きな人向け。
ゲームと呼べるのかわからない作品である。
→というのも、プレイヤーができることは情報ネットワイヤードの中に散らばった音声や映像データを再生することだけである。クリアもゲームオーバーもない。
データは一応時系列順に並んでいるが、好きな順番で再生することができる。
→ゲームというよりも漫画や小説を見ている感覚。
・良かった点
精神疾患を患った少女とカウンセラーの女性とのやり取りが非常にリアルで丁寧に描かれている。
→専門用語のオンパレードだが、それに対し疑問を持ってた少女がカウンセラーに質問してくれるのでプレイヤーが話の内容をきちんと理解できる。大学で心理学や高校で倫理などの授業をきちんとこなしていれば聞いたことくらいはある程度の単語が多々出てくる。
先述のように、データは時系列順に並んでいるがそれが真実とは限らない。それゆえ、自分で話を整理しながら考察する楽しみがある。これがこのゲーム1番の楽しさ。
→再生できるのはすべて音声またはムービーであるためバックログを見ながら考察するということはできない。
この楽しみ方としては、
とあるカウンセリングデータ①のすぐ後のカウンセリングデータ②を再生すると明らかなわだかまりが生じていることがある。その原因を録音したデータを探索発見してメモなどで情報を整理する。
ネットワークに落ちているデータは真実とは限らない。明らかに前後で矛盾しているデータも存在する。どちらが正しいのかを他のデータをもとに考察する。
など。
自分で楽しみ方を見つけられない人には向かない。
とある音声データ(この作品、レインがどのような存在であるのかという核心に迫ったもの)を再生するとその段階までで見つけた映像データがノーカットで再生される。
何が何やらわからないままでいると、全裸のレインがプレイヤーの名前+「これからはずっと一緒だね」と無機質につぶやく。
この演出がとても良い。理解が追い付かない頭でも、何か手遅れな重大なことをしでかしてしまったのだということだけは理解できる。この演出は秀逸。
その意味が分かった時にこのゲームは完結する。
ずっと一緒だね、とは。
存在するということは、その人物の思考パターンや記憶を知ることで成立する。
プレイヤーはエンディングまでにレインのそれを細かに見聞きしてきたことになる。
ずっと一緒とは、プレイヤーが今まで見聞きしてきたレインのことを覚えている限り彼女は存在するということになる。
ここまでを理解できるかどうかでこの作品の評価は大きく変わる。
・つまらなかった点
システム面は酷い。
レスポンスの悪さが非常に目立つ。
メニューを開く、再生するファイルを開くなど何をするにしても数秒間のロードが入る。
再生されるデータの尺は再生するまでわからない。
→ロードに5秒ほどかかったデータが2秒の音声データだったということもある。
ゲーム性がない。
ストーリーの出来は相当ハイレベルであるが、ゲーム性のなさシステム面の粗が目立ち完走しようという気持ちにならない。
しかしこのゲームの行き着く場所、ずっと一緒を実感するためにはこのゲームを1~2日でクリアする必要がある。
・自分であったらどう直すか
ソート機能、ブックマークなどの機能を実装。
矛盾を利用して逆転裁判のようなゲーム性を生み出すこともできるはず。
加筆しますたぶん。
【感想】テイルズオブグレイセスf
テイルズオブグレイセスエフ
これはもはやユーザー目線の感想です。ご注意を。
・ジャンル 守る強さを知るRPG
・開発 ナムコ・テイルズスタジオ
・CMを見て思ったこと
櫻井孝宏氏が声を当てた主人公が、理知的だけれど熱く強い信念を持っている少年に見えて気になっていた。自分はそぅいう主人公が好き。エターニアのリッドのような。
→事前にプレイしていたシンフォニアのロイド、ジアビスのルーク、ヴェスペリアのユーリがあまり好みではなかったので、魅力を感じる主人公に惹かれた。
・実際にプレイして思ったこと
さすがはいのまた氏、キャラクターが良い。女性キャラクターがかわいい。
→ソフィ、パスカルが異常にかわいい。
→とはいえ、キャラデザは正直古臭い。個人的に、新規のユーザーを取り込むことを考えるならいのまた氏の絵は足を引っ張っているように思う。
シェリアには死んでほしかった。嫌いだからではなくシナリオ的に。
パスカルが好きすぎて、ヒューバートとくっつくことが許せない。
個人的にはエターニアの冒頭やファラエルステッドの過去や、ファンタジアの冒頭のような絶望感が欲しかった。
戦闘に関しては3Dになってから初めて面白いと思った。それもかなりの高水準で作られている。
未来への系譜編は個人的には不満。シェリアとアスベルがなぜ…。シンフォニアのようなマルチエンディングにしてほしかった。
・よかった点
人間ドラマが良い。
→子供時代を丁寧に描いていることもあり、登場人物同士の関係が変化していく様や、その変化を通じて登場人物自体が大人になっていく様が良い。
戦闘が面白い。
→デスティニーのチェインキャパ(CC)方式。敵の攻撃を避けて反撃するフェイトアンリミテッドコードのバックステップのようなアラウンドステップ。ポケモンの物理技と特殊技のようなアーツ技(A技)とバースト技(B技)を使い分けて攻撃する。
→アラウンドステップで敵の攻撃を躱し、CCが尽きるまでA技とB技を自由に組み合わせて反撃する。
→避けて攻撃する。これをテーマに戦闘パートを作った時に、今作よりも面白く作るのは難しいと思う。それくらい面白い。
キャラクターに関して。
パスカルの戦闘スタイルは新しいと思った。
→通常技がすべて遠距離攻撃、必殺技がすべて近距離攻撃になっている。
→このシリーズの、好きなキャラクターを操作して戦闘ができる仕様が好きなのだが、自分はかわいいと思った女性キャラクターを使うことになる。すると自然と術使いになってしまっていたので嬉しかった。
→パスカルの戦闘スタイルは独特で、この作品の使用には少し合っていないように感じたが…。敵の遠くでガード、通常技ボタンを連打で勝ててしまう。それに比べ主人公のアスベルは近距離で戦うので、敵の攻撃を避けてその恩恵に預かる楽しさがある。
・つまらなかった点
テイルズオブのセールスポイントであったアニメーションを交えた演出。今作はアニメーションのレベルが高くない。特にOPは。
・どう直すか
OPに関しては直されるべき。
→この後、制作会社が変わって改善された。
いのまた氏のキャラデザは良いが、絵柄まで意識する必要があるのだろうかと思うので、作風にあったタッチにする。
→3Dグラフィックに関しては何とも言えないが、アニメの制作会社が変わってからは幾分かそういう風になった気がする。
→ついでに言えば、テイルズオブシリーズの3Dのグラは質が良くないように思う。
→RPGは存在しないものをいかに存在するように思わせるかが勝負だと思うので、悪い意味でゲームっぽさが目立つグラフィックはよろしくない。
→一応言っておくけれど、筆者はいのまたさんの絵が大好きです。
個人的に、だが移動が面倒だったのでどうにかしたい。
→広大ではないにしても広いマップの移動はRPGをプレイするうえでストレスになることが良く分かった。移動することに恩恵があるアイテムや仕様があるとよいと思う。
【感想】逆転裁判 蘇る逆転(DS版)
逆転裁判 蘇る逆転
・ジャンル アドベンチャー(法廷バトル)
・開発 カプコン
・CMを見て思ったこと
どんなゲームかさっぱりわからなかった。
おちゃらけなゲームかと思いきや硬派な作品だった。
CMの意味がゲームをプレイすることで分かるタイプ。
・実際にプレイして思ったこと
面白い。
戦う、口論するアドベンチャーゲーム。ダンガンロンパまでこういうゲーム性の作品には出会わなかったように思う。
法廷での尋問、つきつけるのための情報を足で探す探偵パート
探偵パートで入手した情報を使って犯人や検察と戦う法廷パート を繰り返してストーリーを進めていく
特に2以降はひとつの事件に対してこの繰り返しの回数が増え、少しずつ事件の全容が明らかになっていく。
・よかった点
レベルデザイン。
→1話は法廷パートのみ、2話はプレイヤーが犯人が誰であるのかが分かった状態でスタートする。3話以降は犯人が分からない状態で進めていく過程でプレイヤーが主人公たちと一緒に推理していく形になっている。
逆転というコンセプト。
→窮地を脱し、さらには真犯人を追い詰めていくシナリオがとても良い。
つきつけるコマンド。
選択肢で話を進めていくのではなく、適切なタイミングでそれに合った証拠を突きつけることでクリアに向かう。
ドットが良く動き、効果音も良い。
→特に真犯人を追い詰めるにつれてテンポが速くなっていく演出は良い。
個人的には主人公が好き。
→真っ直ぐで依頼人を疑わない。矛盾点は徹底的に突いていく。真犯人を逃がさない。熱い好青年なキャラクターが魅力的。
探索パートでの証拠品探しが飽きないように配慮されている。
→脱出ゲームなどにありがちだが、調べる→調べたものの名前+今は役に立ちそうにない。とだけテキストが表示される、なんてことがない。
当たり前となりつつあるが、スキップ機能があり性能は悪くはない。
・つまらなかった点
オカルト要素。
→リアル志向ではないにしても、オカルト要素の存在が大前提の世界観はこの作品に必要だったのだろうか。
→とある死亡してしまうキャラクターを再度登場させるのは良いが、回想などでも置き換えできたように思う。
スパイクチュンソフトの善人シボウデスでもそうだったが、移動したい場所にワンクリックでたどり着けない。
2でも直されていないように思うが、(製作側が決めた)特定の発言に対して(製作側が決めた)適切な証拠品を提出しなくてはならない。
→場合によっては発言と証拠品の組み合わせが正解のそれと違ってもニュアンスが同じことがある。
探索パート(=証拠品を手に入れること)が容易すぎる点。
→探索パートで部屋に入る→タッチペンでタッチ→○○を手に入れた。こういうパターンが非常に多い。また証拠品を入手する順番は任意である。
→これに関しては2以降サイコロジックという形で改善されている。
→証拠品を握っている人間を揺さぶり提出させる仕様になった。
総評。
裁判の面白さ、事実を証明する資料を相手の矛盾に対して叩きつける。これに関しては素晴らしくよく出来ているように思う。
【感想】蒼の彼方のフォーリズム
蒼の彼方のフォーリズム
・ジャンル 恋愛 スカイスポーツ
・開発 sprite
・CMを見て思ったこと
発売前からアニメ化が決定している、ということは知っていた。
スプラトゥーンが遊びを考えるところから始まったという話を聞きつけ、蒼の彼方のフォーリズムもオリジナルのスポーツをテーマにしていることを知り興味を持ち購入。
エロゲは好きだが、見るからに王道な今作はそういう前評判の良さとオリジナルのスポーツ要素がなければ購入しなかったかなと。
・実際にプレイして思ったこと
グラフィッカー、プログラマー、シナリオ、演出… ありとあらゆるスタッフが一流の仕事をした中で、ゲームのデザインをした人間はその域に達していないように思った。
→プランナーが足を引っ張っている作品といった印象。
選択肢が異常に少ない。
→それゆえ共通ルートが苦痛である。
UIが安っぽく使いづらい。
→常時画面全体の1/5ほどを占領するアイコンが表示されていて、テキストボックスが奇妙な場所に配置されていて気持ちが悪い。
最初から最後まで作業だった。
→声優が上手くないので主人公が過去に出会った謎の人物の正体がすぐ分かる。
→よく言えば王道だが、悪く言えばありきたり。こんな風に展開するとは思わなかった。ということがひとつもなかった。別の意味で、こんなシナリオだとは思わなかった。
特定のキャラクターが不愉快。
→スポーツものでやる気のないキャラクターがある出来事をきっかけに努力をし始めるという展開は良い。が、真面目なシーンや緊張感のあるシーンでその雰囲気をぶち壊すヒロインが2人いる。
→ついでに言うとその壊された雰囲気をいつも元に戻してくれるいい娘が攻略対象ではない。それもあって攻略可能なヒロインのことがどんどんと嫌いになっていき、攻略対象外のキャラクターのことがどんどん好きになる。
・よかった点
オリジナルのスポーツ、フライングサーカスをかなり細かく作りこみ登場人物がそれに対してどのような気持ちを持っているのか、どのようなスタイルでプレイしているのかというところまで細かく作り上げていた。
→今作は、実際には存在しないものをどれだけ分かりやすく、よりリアルに描くか。ということに特化していて、非常にすんなりと物語の世界に入っていけた。
リアルな心理描写。
→みさきルート。共感できる、ということがこんなにも大切なことなのかと思わされた。特に今作のような架空のスポーツを扱うような作品では共感できないシナリオや心理描写は命取りだろう。
→ネタバレ注意。努力しなくても人並み以上に何でも修めることのできるヒロインがフライングサーカスを極める努力をして成果が現れない未来を想像して競技自体を辞めようとするシーンが特によかった。
・つまらなかった点
フライングサーカスをプレイヤーはプレイできない。見ているだけである。
→艦これアーケードだと思ってプレイしたらPC版の艦これだった…というような感じだろうか…。
→ゲームに組み込まれていなくても、作戦を立てる段階で選択肢があったりだとかそういったこともない。そこが一番残念だった。
フライングサーカスで攻略不可能と思われた強敵に勝つ。という目的は面白いが、このゲームはそこまでの過程が、シナリオもゲームとしても面白いとは言えない。
みさきルートは真白ルートの分岐の先にある。
→真白ルートのフラグを折ることでしかみさきルートに入っていくことができないが、そういう仕様になっている意味がまるでない。
・どう直すか
ゲーム性を盛り込みたい。
状況が刻一刻と変わるフライングサーカス中に監督として競技中のヒロインに的確な指示を出す、ダンガンロンパのようなゲーム性もよいと思うし、
作戦を立てる。そのためにヒントを探すようなゲーム性もよいと思う。
【感想】セカンドノベル ~彼女の夏、15分の記憶~
セカンドノベル ~彼女の夏、15分の記憶~
ネタバレ注意
・ジャンル 青春-自己-探索-ミステリアス-認識-アドベンチャー
・開発 テクスト
・販売元 日本一ソフトウェア
・CMを見て思ったこと
フリーのノベルゲーム、TRUE REMEMBRANCEを現代の高校生、青春をテーマに描いたらこんな感じだろうか。
過去を想いながら今を生きていく女の子、もしくは寿命を迎える直前の女の子の話だろうかと思った。
エロゲによくあることなのだが、CMに使われているグラフィックの種類が多すぎて初見のプレイ中に初見ではないグラフィックをたくさん見ることになる。
この作品はそのパターンだと思った。
。
・実際にプレイして思ったこと
冒頭のとあるテキストが表示された時点で、今を生きていく人間たちを描いた物語ではないことが分かった。
さらに言えば、過去の改ざんや記憶の書き換えを行うわけでもないので救いがない。しかしながらオカルト要素は満載。
→オカルト要素があるのならばそれが救いの方向に働いてもよかったのではなかろうかと思った。
おまけ小説、ファーストノベルの完成度が高い。
→個人的には田中ロミオ氏、唐辺葉介(瀬戸口廉也)氏の物語が好きで、この作品を機に両氏の作品に触れるようになった。
→セカンドノベルがそういった触れる機会の少ない作品に触れるきっかけを作るために作られたものだとするのならば大成功なのだが…
ストーリー
夏の休暇を利用し、久しぶりに故郷に戻ってきた直哉は、高校時代の友人・彩野と再会する。だが、彩野は5年前の事件の後遺症で15分しか記憶を留められなくなっていた。
直哉とともに過ごす内、彩野は「彩野が高校時代に書いていたという物語」という、今まで思い出すことのなかった記憶を取り戻していく。
その記憶を繋ぎとめようとする直哉は、15分という限られた時間の中で、物語を少しずつ紙に書き留めていく。
ゲームの流れとしては、
記憶が途切れる病を抱える彩野から15分に相当する話を聞いて、少しずつ話を選択肢によって整理し、1日の終わりにそれをダンガンロンパのクライマックス推理のように話をまとめていく。過去の話を聞く→まとめる→1日の終わりに考察、残った謎を解く選択肢なしのシナリオが始まる。を繰り返す。
選択肢は逆転裁判のようにキーになるもの言葉を見つけるたびに増えていく
・良かった点
ストーリーとシステムがとてもうまくシナジーしている。
どちらともいえることだが、仕様ゆえに同じ話を何度も読まされる。
→数日ぶりにプレイするときにはありがたいが、連続でプレイする分には非常に煩わしい
シナリオの完成度が高い
→中だるみがないわけではないが、各章伏線の回収をきちんと行っていて後半に熱くなれる展開が必ずある
→オカルト的な内容ではあるが奇跡などに頼らずにきちんと話を作っている
→現実にも起こり得る身体的な障害を扱っているため、強すぎるファンタジー色は合わなかったのだろうと思う。リアルな部分はリアルに描かれているために、結局は救われないシナリオというのも記憶障害は適応規制のひとつであって、それは忘れないと生きていけないからそうなったということである。
その原因となった過去を主人公は辿っていくわけで、進めば進むほどどんどんと暗くなっていくため好き嫌いがはっきり分かれると思う。
キャラクターが良い
→安易にビジュアルや萌えに走らず、人として魅力的に思えるように描かれている
・つまらなかった点
数多くのノベルゲームを作ってきた会社とは思えない稚拙なUIとシステム面
よくあるADVとは違った分岐というシステム。物語が分岐する箇所はいくつもあるが、ノーヒントでは見つけることが困難。しかしそれを見つけない限りストーリーは進んでいかない。
絵が上手くない。
→立ち絵が同一人物なのか、声を聞くまでわからない
システムメッセージの表示回数が多すぎる。
使用可能なキーワード(=選択肢)が増えることでストーリーを進めれば進めるほど難易度が上がるはずが、ヒロインから「○○を選んで」といったヒントどころか答えが与えられてしまっていてゲーム性が著しく損なわれている
一人称が統一されていないなど、文章に粗がある
語り手が変わったときにそれを気付かせる演出がない
主人公の青年は、大切なことを口に出せない性格という設定があるが、すべきこと必要なことをやらない シーンが多く非常にイライラする
→虐待の黙認。シナリオ上、この設定は全く必要がない
シナリオ面でヒロインの過去を彼女の口から聞いていく設定をうまく生かし切れていない
→他人の口から過去を聞くという設定なので、真実と虚構の境界線を曖昧にすることで前後の矛盾などからプレイヤーが考察をしながら楽しむという作りにできたはずだがそれが無い
さらに言えば、
真実が明らかにされない
製作者のコメントを見てきたのだが、答えはプレイヤーの中にある とのこと。
考察をさせるゲームとしてはありなのかもしれないが、個人的には怠慢のように思える。
制作サイドが隙間を用意せずとも二次創作や考察というものは良い作品には自然とついてくるものだと考える
スキップ機能が使いにくい。非常に遅い
・どう直すか
シナリオ面
前述したが、身体的な障害を扱うということはそれに向き合うということがテーマになっていく。そのためにシナリオはへヴィで暗いものになっていく。
今作はそういった重苦しさを、ビジュアル的に利用しオカルト要素を混ぜることで上手く中和しているように思う。
が、物語冒頭でヒロインの記憶を司る海馬領域が死滅していて高校生の夏から時間が進んでいないと明記してしまったがために、救済の要素もなく最後まで彼女は永遠の夏に閉じ込められたままである。
救おうが救うまいが賛否両論になるだろうが、生きていく理由や希望といったものを見つけて終わってもよかったのではと思う。それも結局忘れてしまうことになるのだが…。
【感想】俺の屍を越えてゆけ(PSP版)
俺の屍を越えてゆけ(リメイク版)
PS版、PSP版、vita版の2すべてプレイしました。
作中の言葉ではわかりづらい表現はわかりやすい言葉に置き換えています。
・ジャンル ロールプレイングゲーム
・開発 アルファシステム
・販売元 ソニー・コンピュータエンタテインメント
・CMを見て思ったこと
1と2のCMが連作になっていて、面白い。
パッケージもそうだが、CMも一度見たら印象に残る。
ゲームのタイトルが作品のコンセプトそのままになっているからだろうか。
・実際にプレイして思ったこと
シナリオとシステムのシナジーが素晴らしい。
装備、レベルアップの他にステータスをアップする方法があるゲーム。
自分でストーリーを作っていくRPG
ダビスタのような育成ゲーム、シムシティのようなシミュレーションゲームとしても楽しめる。
→やりこみ要素が多いゲームが好きな人は好きなゲームだと思う。
繰り返しになってしまうが、やることではなくできることが多い。
→お楽しみ要素が強く、なくても困らないコマンドが多い。
→家族をテーマにしたゲームならではの要素も強い。
お金のやりくりが非所に重要。
・よかった点
時間に追われていくシナリオ、ダンジョンに緊張感がありプレイングを考える楽しみがある
一族が強くなっていくことを実感できる調整がなされているし、同じダンジョンを繰り返し攻略することにも飽きが来ないように配慮されている
→前者は、1年に1度の選考会で同じ敵と戦うことになるのだがトーナメント形式で順調にプレイしていれば1~2年で前回よりも上へ行けるように調整されている
→選考試合は実際に攻略には関係がないが、貴重な(金になる)アイテムを手に入れることができる。
→後者はダンジョン攻略に時間制限があり、強くなるほど短時間で奥まで進めるように調整されている。
プロローグで戦闘システムをほぼほぼ理解できるように、ストーリー上でチュートリアルを上手く兼ねている
シナリオ上、プレイヤーキャラクターがどんどんと変わるがそれに伴う煩わしさは感じない。
→装備の変更を頻繁にする必要があるが、適当な装備を自動でつけてくれる。
→個人的にはその機能が必要かどうかと考えてしまう。どのキャラクターが使っていた装備なのかが表示されることで思いをはせることができそうだと思う。
戦闘が楽しい
難易度を選ぶことができて難易度によっては流れ作業では
→敵を倒した時に手にアイテムが戦闘開始時にスロットで決定される
→HPが0にならずともプレイヤーキャラが死んでしまう可能性があるので、それを念頭に置きつつ戦う楽しみがある
→相手の大将を倒すことで戦闘を終了することができるので戦闘も苦になりづらい
→経験値とは別に、子孫を残す際に必要なポイントが手に入りダンジョンから帰還したときの楽しみになる
→敵を倒すことで子孫を残すためのキャラクターが解放されることがある
→家族でダンジョンに挑む設定ゆえに、庇うコマンドに愛を感じた
→ダンジョンの新しい階層に辿りつくたびにストーリーに関わる小話を聞くことができる
育成ゲームとしてはダービースタリオンに近いシステム
→神との交配である程度のステータスが決まった子供が生まれ、それを教育やダンジョンで強くしていく
→神との交配で親のステータスを引き継いだ子供が生まれて家計を強くしていく
・つまらなかった点
装備に関しては熟練度や、家族の誰が使用していたのかを表示させてほしい。
→家族の思いを受け継いでいくゲームだが、アイテムにはそういう気持ちを感じさせる工夫が見られない。
ダンジョン内で背景が変わらないため奥に進んできた実感が薄まってしまっていると思う
→色を変えるだけでも違うはず
ダンジョンでのプレイヤーキャラの当たり判定が大きく、うまく前に進めないことが多々ある。制限時間の存在もあってイライラに繋がる。
→当たり判定を小さくする
ダンジョンの数が少ない
→先代が成し遂げられなかったダンジョンを子供が攻略するこのゲームの性質上、ひとつのダンジョンが長く難 しいものになるのは分かるが、だとしても4つだけでは少なく感じたので増やすべき
→俺の屍を越えてゆけ2では、遠征システムが追加されてダンジョンの数が増えた
ボスが強くはないが死なない
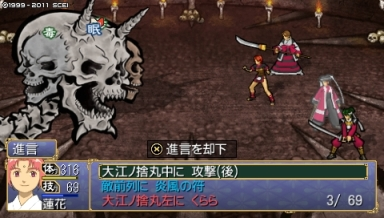
→この手のボスは左右のどちらかが回復役でそれを倒してから本体を叩くのがセオリーだと思う。しかしその実は一番耐久のある中心の髑髏が回復役で復活魔法まで使うため、負けることはないと分かるダメージを受けながら倒すことができずに時間が過ぎていく。これを修正するべき。敵キャラクターの見た目からどんな戦術が有効なのかが非常に分かりにくい。
→キャラクターのHPが0になる=死亡 もう二度と戻ってこないという仕様だが、初見殺しが多いように思う。
→このゲームで家族を一人失うということはゲームオーバーや詰みが見えてくるほどの大事故なので、初見殺しでの理不尽さは他のゲームよりも深刻。
総評
システム、シナリオ共に素晴らしい。リメイク版としても細かなところに手が加わっていて素晴らしい。ストーリーを自分で作っていくタイプのゲームで、理不尽さすら楽しめる人は楽しめる。
→死亡するまでに成し遂げたこと、どこで死亡したのかをいつでも見直すことができるのも良い。いろいろな遊び方で何度でも遊ぶことができる素晴らしいゲームだと思う。1週目と同じ家族でIFのストーリーを作るのも良いし、新しい家族で効率を求めるのも良い。
【感想】オーバーウォッチ オリジンズ・エディション PS4版
オーバーウォッチ オリジンズ・エディション PS4版
・ジャンル アクション・シューティング
・開発 ブリザードエンターテイメント
ハースストーン、スタークラフト、ディアブロ、ウォークラフトシリーズの会社
・CMを見て思ったこと
よくあるFPSとの違いは判らなかったが、大人数であることや本格的な戦争であることよりもキャラクターの可愛さ格好良さを推すゲームのように思った。
・実際にプレイして思ったこと
FPSに足りなかったキャラゲー要素が強い。総勢23人のキャラクターが存在し、キャラクター同士でビジュアル、性能、性格が被らないように作られている。
→キャラクターには4種類のロール(役割)の中から1つが割り振られていて、自分のプレイスタイルに合わせたりチームに必要なキャラクターを考えてキャラクターを選ぶ。
→同じロールのキャラクターでも尖っている性能や得意なステージが被らないように作られている。
FPS+MMORPGのようなゲーム性を理解しているプレイヤーこそこのゲームでは強いプレイヤーであり、CoDのようなFPSが得意なだけのプレイヤーには向かない。
スプラトゥーンなどと比べて、キャラクターそのものが意思疎通に使える。
→前線に立って活躍できるキャラクターと後方支援をすべきキャラクターがきっちりと別れている
→スプラトゥーンは見方がどんな武器を使用しているのか勝負が始まるまでわからないが、オーバーウォッチには準備時間が設定されているうえに勝負の最中にもキャラクターの変更が可能。
・よかった点
誰もが自身の活躍を実感できるようにできている。キル数だけが活躍じゃない。
→ゲームに参加しているだけでも活躍できるキャラクターがいる。
→例えば楯役のラインハルト、近くにいる見方を無条件に回復させ続けるルシオ、設置武器を有しているトールビョーンやシンメトラ。
→またゲームには直接関係ないが、リプレイの自動保存やTwitterへの連係機能、ベストプレイヤーを勝負の最後に発表するシステム、達成したタスクを事細かに記録し閲覧可能である点も良い。
→自分以外のキルデス数を表示せず、味方の情報は活躍のみを表示している。
チームプレイをテーマに掲げているところが良い。
そのためにすべてのキャラクターは、性能が良い意味で尖っている。
しかしながら、1対多数の状況をひっくり返せるキャラクターはプレイした限りでは存在しない。
基本的に2人以上で行動すれば相手が単独行動をしている場合はほとんど勝てる。
このバランス調整は素晴らしい。
プレイしていて、勝負が始まる前から勝敗が決しているような状況に出くわしたことはほとんどない。
上手い人が一人で活躍するゲーム性でないところが素晴らしい。
フレンドがおらずひとりでプレイしている人間にも、フレンドを作る機会を与える「現在のチームを維持する」コマンド。
→試合の終わりにこれを押すことで同じチームでプレイしたプレイヤーにその意思を伝えることができる。
マップのデザインが良い。
→高低差や裏取りのための小道、設置武器を置くことができる場所が多々ある。
キャラクターの性能を確かめながらゲームを検索できる。
戦況をひっくり返す必殺技がある。
→その必殺技への解答もある。
・つまらなかった点
キャラクターの性能に格差がある。
→体力が高いキャラクター、攻撃力の高いキャラクターが強すぎる。
マップ、ルールが選べない上に少ない。
・どう直すか
オーバーウォッチをプレイして、こうだったらいいのにな… が次々にアップデートで改善されていく。
シンメトラのアーマー付与が役に立たない、単独でマルチプレイをしているのが辛い、同じキャラクターをパーティ全員が使用したいが誰も譲らない。といったつまらなさが改善された。
FPSには数字にこだわるプレイヤーが多いが、オーバーウォッチはそういうゲームではないという点が、特定のプレイヤーのストレスになっているように思う。
→過程を楽しむタイプのこのゲームでは、結果を重視する人間には辛い。
→キャラクターごとにデイリーミッション(例えばキル数や回復量など)を用意し、達成することでアイテムや通貨を貰えるようにするのはどうだろうか。
ここまで書いていて思ったことが、ゲームをどう調整するのかを考えることもも大切だが、どう運営していくのかを考えることも必要になったのだと痛感した。
【感想】不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス
不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス
・ジャンル ローグライクゲーム
・開発 チュンソフト
・CMを見て思ったこと
あ、また新作が出るんだ… とただただそれだけを思った。
ポケモンのように、ある種完成されたゲームであるのでどのように新しくなったのかは楽しみだった。
・実際にプレイして思ったこと
おもしろいが画質が良くなっただけのようにも思った。
不便だった部分はかなり改善され、難易度は下がったように感じた。
1000回遊べる、という宣伝文句は今作では言い過ぎに思う。ああ
・よかった点
つまらなかった点と表裏一体であるが、昼夜でゲームのあり方が変わるシステム
夜にだけ使える強力な技
装備が成長するシステムとタグシステム
→冒険の度にレベルが1になる主人公の代わりに装備が強いままスタートできる
→タグをつけることでなくしてしまった装備が手元に戻ってくる
持つことができるアイテムの数に制限があるため、ダンジョンを進めていくうちに取捨選択を繰り返すことになる
→頭を使いながら進めていくパズル的な要素が面白い
シンプルで非常に使いやすいUI
→必要なときにマップや位置関係を把握するためのマスが表示される

・つまらなかった点
投げたもの、遠距離攻撃がまず当たらない
難易度の調整の仕方が、落ちているアイテムが識別済みか未識別かという点
→落ちているアイテムを拾う→それが何だかすぐには分からない→回数制限のある識別アイテムを使用という流れ
昼夜でステージのあり方が変わるのは良いが、夜の敵はプレイヤーキャラクターに向かって来ないのでその場で足踏みをして時間の経過を待つことで簡単に朝を迎えることができてしまう
運ゲーの要素が強い
→マップと敵の配置や、落ちているアイテム次第で難易度が激しく変わってしまう
オンラインでの協力プレイを前提とした難易度設定と救済のシステム
・どう直すか
命中率の上がるアイテムの数を増やすべき。もしくは遠距離攻撃の命中率を上げる
全体的に難易度の高さゆえにストーリーが進まない点を直すべき
→幸運の腕輪(1歩進むごとに経験値が1貰えるアイテム)が無いとまずクリアできないといったような持つべき&捨てることのできないようなアイテムが存在していて、そのせいで手持ちのアイテムが制限されてしまう。このゲームは上手くアイテムのやりくりをするところに面白さがあると考える。
→所持できるアイテムの数を5つでも程増やすだけでも解消できるようになると思う。
ステージに配置されたアイテム、店頭で売っているアイテムが未識別なのは良い。使ってみて効果を確かめる楽しみもあるし、店頭での価格から何のアイテムかを予想する楽しみもある。しかし進めていくうちに、おそらくこのアイテムはあれであろうが一応識別しておこうか…といった、識別をしぶしぶされられている感覚になってくる。
→落ちているアイテム、一度識別したことのあるアイテムは識別済みの状態で落ちている、売っている仕様で良いと思う。
【感想】パワプロクンポケット9
パワプロクンポケット9
僕はパワポケシリーズが本当に好きです。その中でも7→9の流れが特に。
・ジャンル 野球バラエティ
・開発 コナミデジタルエンタテインメント
・CMを見て思ったこと
今作に関してはCMを見たことがない。
作中で見ることができるが、ネタのひとつでしかない
・実際にプレイして思ったこと
野球部分が面白くなった。
→リアルな上にゲームとして成立する調整がなされた。7の人間が追い付くことのできない理不尽な打球のスピードや、8の広すぎるストライクゾーンや打ちづらかったのミートカーソルなど
・よかった点
野球バラエティと銘打っただけあって、野球に関わる面白さ(特に今作は社会人の草野球)を掘り下げている。
→野球自体の面白さは攻撃側の 打つ 守備側の 投げる を掘り下げる、携帯機の低スペックを煩わしく感じさせない作りになっている。これに関しては現在のiOS版などのアプリにまで受け継がれているように思う。また、難しかった守備も打球が飛んだ方向がかけ声が表示されるようになって遊びやすい
→社会人の草野球に関しては、大手スーパーに負けそうな商店街を舞台に、人間関係を上手く描いている。社会人の野球の在り方を面白く切なく作品に落とし込んでいると思う。
シリーズであることを上手く利用している。
→自分はシリーズものでストーリーに繋がりがある作品が好きであり、パワポケシリーズの魅力の一つはそこにあると思っている。
具体的に言えばパワポケ7の流れを意識して作られている点。
→7では高校の野球部にどんどんと転校生がやってきて野球部が乗っ取られていく… といったストーリーだったが、今作は主人公が助っ人側になる。また主人公に惹かれたキャラクターたちが「自分にも野球をやらせてくれ!」と言ってどんどんと部外者が野球チームに加入していきそれがもとでチームの中で争いが起きる… と言ったような。
→さらに、明言はされていないが今作の主人公は7の助っ人第1号のレッド同一人物だと考察できるような台詞がいくつか存在する。そういう考察をすることで7ではチームを壊滅させてしまった助っ人がもう一度同じような形で野球に挑む物語になる。
彼女のシナリオも良い
→今作はホームレスの主人公が自分を養ってくれる彼女を見つけることで心身ともに強くなっていく部分があるので、ぎりぎり野球とも繋がりつつそれがなくとも読み続けたくなるような爽やかでどす黒いシナリオ。
→個人的に人間じゃない女の子との恋愛を描いた作品が好きなので嬉しかった。他にも、夢を追いかける劇団の女の子、商店街でカレー屋を営む未亡人、第一印象最悪からスタートするレストランの店員、主人公を餌付けする物静かな女性など… キャラクターがそろっている。
→グッドエンドでは、7の助っ人であり9で主人公になったレッドが、確かな幸せを大切な人と共有するものが多い。
彼女以外にも人間じゃない、もしくは人間らしく生きることを辞めたキャラクターが多いが、それぞれが憎めない人間らしさを持っている。
シナリオに関しては、正史と呼ばれるシリーズを通してのストーリーがあるためにキャラクターによっては無情な結末を迎えているものもある。
→パワポケシリーズはダンガンロンパやクラナドのようなキャラクターを殺すことで魅力を引き出している作品だと思う。
総じて、野球を絡めたシナリオ、キャラクターの質が高い。
シリーズである強みを外伝的なシナリオにすることで生かしている。
野球も9までのシリーズを見た場合には良い出来。
・つまらなかった点
仲間になるキャラクターで優秀な投手が少ない。
→仲間に出来る投手は3人。仲間にするためには複数のターンの消費が必要であり、ランダムイベントなので場合によっては時間を浪費するだけになることも。
監督の采配がめちゃくちゃ。
→DH制なしでの試合ゆえ、ピッチャーの打順ではすぐ代打を出される。
→そこら辺の野手よりも打者としての能力が高い投手がいても打順が来るとすくに代えられてしまう。
また、優秀な投手がいたとしてもストレートしか投げられない投手が起用されることもある。
つまらないとは言わないが、シナリオはあっさりめで7や8のような深みはない。
→前述したが野球を絡めた、というよりは野球が掠っているシナリオである。7や10のような「自分には野球しかない」といった主人公が好きな人には面白く感じられないかもしれない。
【感想】ジャック×ダクスター
ジャック×ダクスター 旧世界の遺産
・ジャンル アクション
・開発 ノーティドッグ
・CMを見て思ったこと
一度見たら忘れない。
上に貼った動画とは別のバージョンが、俺たちずっと友達だよな!もし俺がイタチになっても!みたいなCMだった気がする。
このCMを見てPS2が欲しいと親にねだった。
自分はここからゲームにどっぷりはまっていった。
スーパーマリオ64をオープンワールドにしたようなゲーム
クラッシュバンディクーのような奥スクロール感が強く、無双シリーズのような敵の倒し方よりもジャンプを起点にしたアクションで敵を倒す場面が多い
バイオハザード5やメタルギアシリーズのようなトライ&エラーが好きな人向け
・良かった点
難易度調整が絶妙で、簡単すぎず難しすぎない
→プレイヤーキャラクターが体力が4つで0になると死亡する。しかし大抵は落下によって死亡するため、この体力設定は敵の処理を誤った時に有難い
→制限時間や、強制スクロールがつくステージがあるがそれもぎりぎりクリアできるように調整されている
残機制ではないので何度でも挑戦でき、チェックポイントから再開しロード時間も1秒ほど
→この仕様が調度よいと感じる難易度に作られていて、10分ほど頑張ればどのステージもクリアできるようになっている
チェックポイントの位置が絶妙で、オープンワールドにありがちなステージ間の移動中に感じるストレスが軽減されている
マップ上に落ちている時間限定で使える、加速、回復、遠距離攻撃、攻撃力アップのアイテムの配置が良い
→プレイヤーキャラクターが強化されてさくさく進めていける爽快感
→また時間制限のために生まれる緊張感?が良い
細かな背景まで書き込まれたグラフィック、時間経過で変化する太陽の位置など視覚的に飽きることがない。
→今作では昼と夜で性能や挙動が変わるものはない。PSP版はソニックワールドアドベンチャーの様に昼と夜でゲーム性が変わる仕様が追加された
オーブ(マリオで言うコイン)やテイサツバエ(マリオで言う青コイン)といったアイテムの設置位置が考えられていて、探さないと取ることができないが高度な技術は必要ない
簡単に派手なアクションを出すことができ、それらを使用するギミックが多く存在する
→ジャンプとパンチを組み合わせたヒップドロップや、パンチとジャンプを組み合わせたアッパー、ジャンプと回転蹴りを合わせた滞空時間を延ばすジャンプ、回避移動とジャンプを組み合わせた大ジャンプなど
・つまらなかった点
キャラクターの会話に字幕がなく、2度と聞けない話が多い
ストーリーが面白くない
→○○が盗まれた取り返してくれ…の繰り返し
キャラクターは主人公たち以外基本的に使い捨て
プレイヤーキャラクター(ジャック)が死亡した際に、相棒(ダクスター)による煽り演出が入るが非常に憎らしい
→死んで覚えるゲームなので各ステージで必ず見ることになる
→通算死亡回数が一定になるとこの演出がなくなるのは良い仕様
ステージは広大だがマップがない
強化アイテムは、時間で無限に復活するために難易度が下がってしまう
→特に遠距離攻撃ができるアイテムは安全に遠くの敵まで倒すことができてしまう
アクションは多彩であるがそれを受けきれる敵がいない
→基本的に敵は一撃で死んでしまう
→しかし終盤では敵に囲まれる場面が増え
無双シリーズのような感覚でコンボを
決めていける
カメラの位置が良くない
→コナミカメラの特許ゆえ、壁の近くに
キャラクターがいると画面が安定しない
・どう直すか
デザインが悪いわけではないが、
キャラクターのデザインが明らかに
日本人向けではない。
→超人的なアクションが多い上に、
人間がイタチに変えられたという設定が
あるのだから、
風のクロノアのような獣+人のような
デザインにしても良いと思う。
ストーリーを進める楽しみはストーリーを作りこむしかないが、キャラクターを使い捨てることに関してはお使いイベントなどで解消できると思う。
強化アイテムに関しては拾うたびに貯めておいて、使用したいときに使用して止めたいときに止めることができる仕様にする
プレイヤーキャラクターが死亡した際には、相棒からは煽りではなくヒントが貰えるようにする